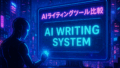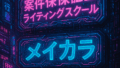AIライティングが一般化した2025年、文章の「品質」をどう担保するかが新たなテーマになりました。
本記事では、国産AI校正ツール3強であるTypoless・Shodo・文賢を横断比較し、それぞれの精度・提案力・使いやすさ・チーム運用性を徹底検証します。個人ライターから企業・メディア編集部まで、目的に応じた最適ツールを選ぶための完全ガイドです。
気になるツールがあれば、まずは公式サイトとAI Workstyle Labの解説記事をセットでチェックしてみてください。 「機能の概要 → 実務での使いどころ」の順に見ると、自分の環境に合うかどうか判断しやすくなります。
文脈を読み取って自然な日本語へ整える「提案型AI校正」。個人ライターから中小企業の広報・制作チームまで、 コスパ良く“読みやすさ”を底上げしたい人におすすめです。
朝日新聞社の10万件ルールをもとに、誤表記と炎上リスクから「言葉の信頼」を守る校正ツール。 公的文書・IR・プレスリリースなど、社会的信頼が重要な文章に向いています。
ウェブライダーの編集ノウハウを凝縮した、Webライティングに強い校正・推敲ツール。 SEO記事・オウンドメディア・教材など、「伝わる文章」をチームで育てたいときの本命候補です。
※料金・機能は執筆時点の情報をもとに記載しています。最新情報は必ず各公式サイトでご確認ください。
この記事でわかること
- AI校正ツールの基本仕組み(提案型AIとは?)
- Typoless・Shodo・文賢の強みと違い
- 文脈理解・提案力・表記統一など精度の比較
- 個人・企業・編集チーム向けの最適ツール選び
- 料金プラン・導入ハードル・セキュリティの違い
- 文章品質が上がる活用ワークフロー(ChatGPT連携)
- AI校正のメリットと限界(人の判断は必要?)
- チーム導入でのポイント(権限管理・ルール共有)
- 無料で試せるツールとトライアル情報
- 2025年に選ぶべきAI校正ツールの結論
AI校正ツールとは?|提案型AIが変える文章品質
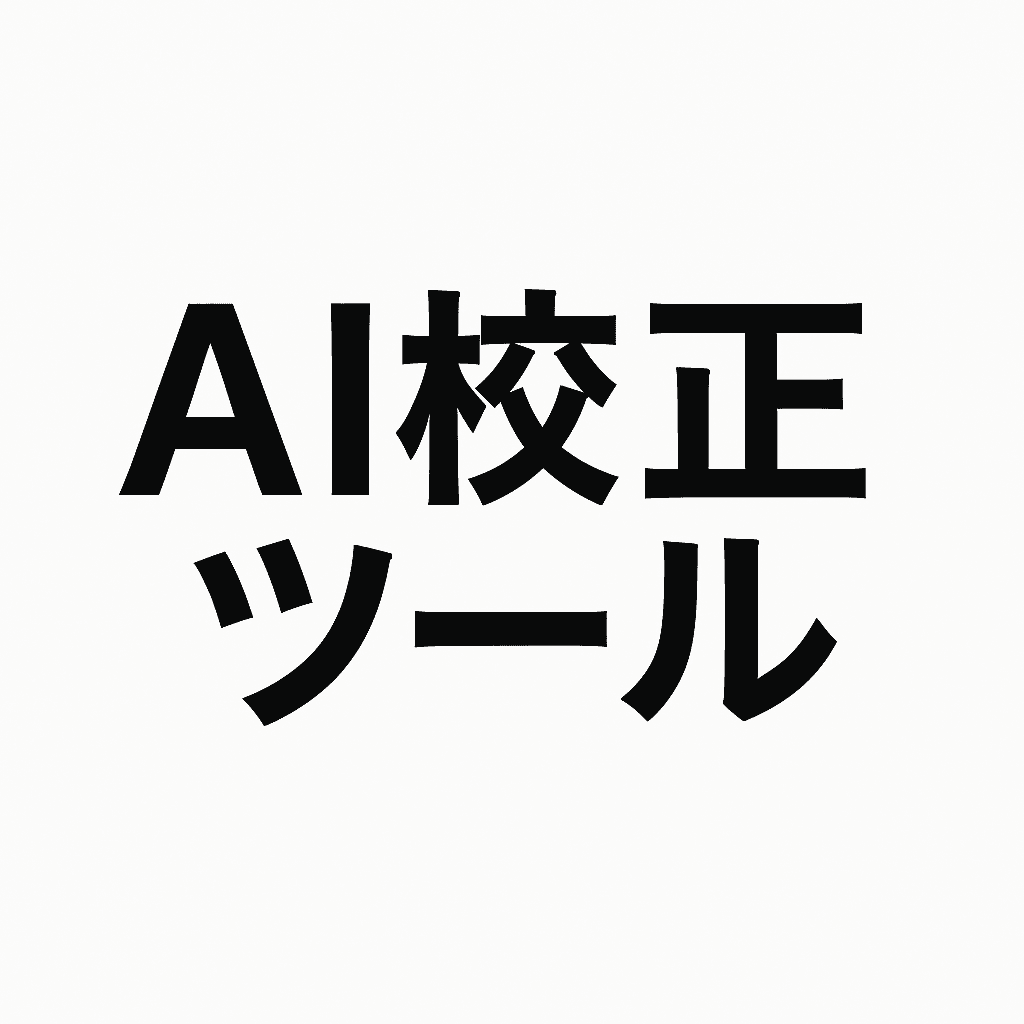
AIライティングが一般化した2025年。
誰もがAIを使って文章を生み出せるようになった今、次に問われるのは「どれだけ正確で、伝わる文章が書けるか」です。
かつての校正作業は、誤字脱字を探し、表記ゆれを直すだけの後処理でした。
しかし現在のAI校正ツールは、文脈理解・語彙提案・文体統一・敬語チェックなどを自動で行い、「どうすればより良い表現になるか」を提案する提案型AIへと進化しています。
この提案型AIの登場により、文章の品質管理は人が直すからAIと共に磨くへ。
企業や編集チームでは、AIが社内ルールを理解して自動で校閲する時代になりました。
また、AI校正ツールはライターや企業だけでなく、教育現場でも活用が進んでいます。
学生のレポート添削、社内ドキュメントの表記統一、SNS発信のリスクチェックなど──
「書くこと」そのものが多様化する中で、言葉の品質を担保するAIの役割が急速に高まっています。
主要AI校正ツール3選【Typoless/Shodo/文賢】
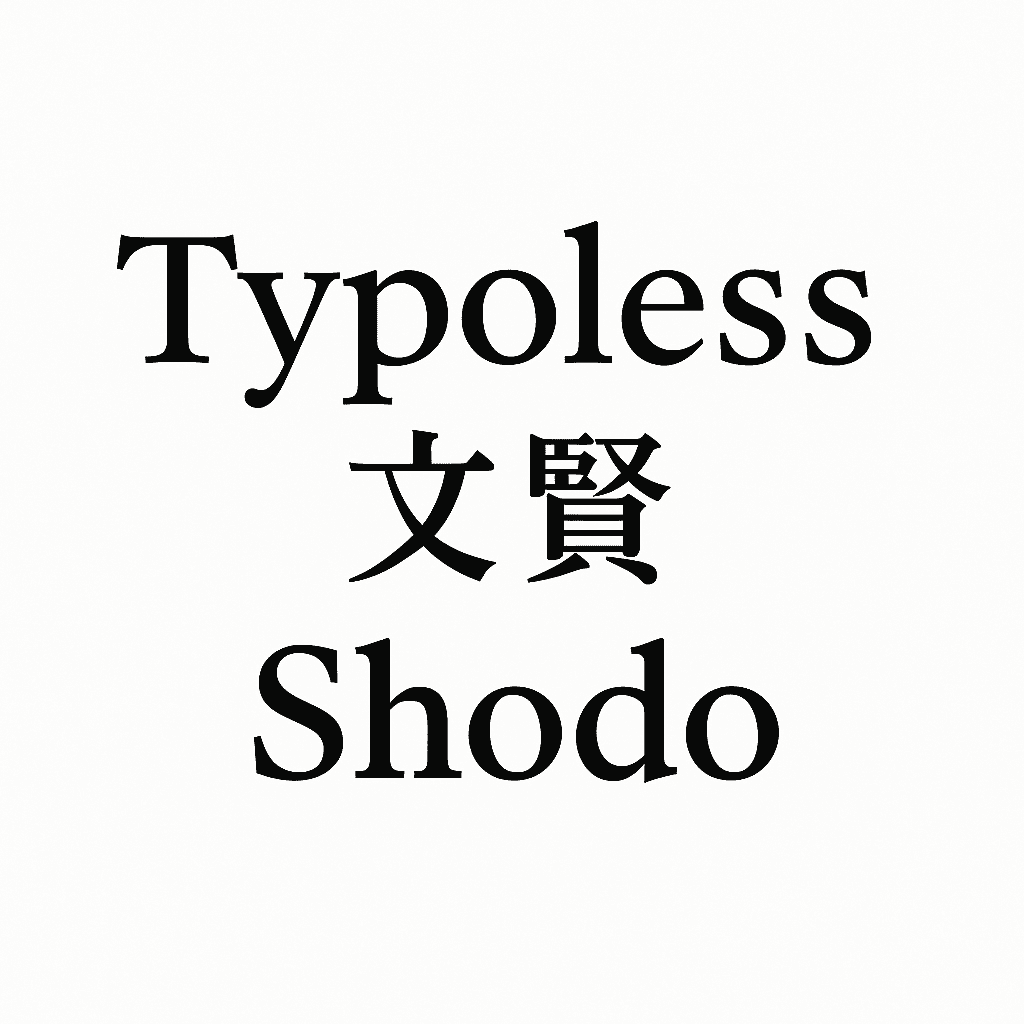
AI校正ツールの総合比較
Typoless・Shodo・文賢は、一見“AI校正ツール”という同じカテゴリに見えますが、実は得意領域も設計思想も大きく異なります。この総合比較では、3ツールのコンセプト・強み・弱み・料金を俯瞰し、「どのユーザーがどれを選ぶべきか」を最短で判断できるよう整理しました。まずは全体像を掴むことで、後半の詳細比較もより理解しやすくなります。
Typoless・Shodo・文賢の総合比較
| 項目 | Typoless | Shodo | 文賢 |
|---|---|---|---|
| コンセプト | 朝日新聞社の10万ルールをもとに、 誤表記と炎上リスクから「言葉の信頼」を守るAI校正DX |
文脈と意図を読み取り、 自然な言い換えを提案する「提案型AI校正クラウド」 |
ウェブライダーの編集知識をAI化した、 ライターと共に文章を磨く「共創型校正ツール」 |
| 得意領域 | 公的文書/報道/IR資料/PDF冊子など、 社会的信頼が重視される文章 |
Web記事/ブログ/社内文書など、 「読みやすさ」と自然な日本語が重要な文章 |
SEO記事/オウンドメディア/教材/コピーなど、 伝わりやすさと説得力が求められる文章 |
| 主なターゲット | 官公庁/大企業広報・IR/報道機関/大学・研究機関 | 個人ライター/ブロガー/制作会社/企業内の執筆担当 | Webライター/編集者/Web制作会社/コンテンツマーケ部門 |
| 強み | 差別表現・ジェンダー・地域・宗教などの センシティブ表現と炎上リスク検知が圧倒的に強い |
提案が軽快・自然で、「AI編集者」が隣にいる感覚。 無料〜プレミアムのコスパも高い |
辞書共有・ルール校正が強力で、 チーム全体の文章トーンをそろえやすい |
| 弱み・注意点 | 個人ライター視点ではややオーバースペック/価格帯高め。 創作・比喩の自由度より「正しさ」が優先されやすい |
メディア品質の厳密なルールチェックではTypoless/文賢に劣る場面も。 無料版は制限あり |
初期費用+月額でコストは高め。 ライトな個人利用にはオーバースペックになりやすい |
| 個人向け料金イメージ | スタンダード 2,200円〜/月(税込) | プレミアム 1,000円/月(税込)※無料プランあり | 初期費用 11,880円+月額 2,178円(税込) |
| チーム導入の適性 | ◎ 大企業・官公庁のガバナンス重視の利用に最適 | ◯ 中小企業の広報・制作チームに導入しやすい価格&機能 | ◎ 編集部や制作会社の「文章品質統一ツール」として最適 |
| 一言で言うと | 「社会的信頼を守る、新聞社発のAI校正DX」 | 「ライターの隣にいる、提案型AI編集者」 | 「書く力を支える、共創型の文章パートナー」 |
・Typoless は「信頼性」と炎上リスク対策に最適なAI校正DX。
・Shodo は自然な日本語で“読みやすさ”を整えたい個人・企業に最適。
・文賢 はSEO・Web編集で、チーム全体の文章品質向上に強い本命ツール。
校正精度の比較
AI校正ツールの選定で最重要となるのが「どこまで正確に文章を直せるか」。誤字脱字・表記ゆれ・敬語・炎上リスクなど、文章の土台となる要素はツールごとに得意分野が分かれます。Typolessは新聞社レベルの厳格なチェック、Shodoは文脈理解による自然な提案、文賢はWeb文脈・SEO記事での読みやすさ向上が強みです。用途に最適な精度感を明確に比較します。
校正精度の比較
| 項目 | Typoless | Shodo | 文賢 |
|---|---|---|---|
| 文脈理解の精度 | ◯ 文脈の不自然さも検知するが、ルールベース寄り | ◎ 生成AIを活用した文脈理解で自然な提案が得意 | ◎ 意図を踏まえた提案で、読ませる文章に調整しやすい |
| 誤字脱字の検知 | ◎ 新聞社レベルの誤表記辞書で網羅的にチェック | ◯ 一般的な誤字は問題なく検出 | ◎ Web制作現場でも定評のある検出精度 |
| 表記ゆれの統一 | ◎ 新聞基準で統一候補を提示 | ◯ 表記ゆれ設定により一定レベルの統一が可能 | ◎ 辞書とルールで、媒体ごとの表記統一に強い |
| 助詞・助動詞の自然さ | ◯ 誤用は的確に指摘 | ◎ 自然な日本語への言い換え提案が多い | ◎ こなれたWeb文体への調整が得意 |
| 専門用語への対応 | ◎ 報道・ビジネス寄りの専門表記に強い | ◯ カスタム辞書前提で対応可能 | ◯ Webマーケ・ビジネス文脈には十分対応 |
| 敬語・二重敬語チェック | ◎ 敬語の誤用を厳密に検知 | ◯ 主要な誤用は検知 | ◎ ビジネスメール・LPなどの敬語調整に強い |
| 炎上リスク・センシティブ表現 | ◎ 差別表現・偏見・ジェンダーなどのリスク検知が強力 | △ 専用リスクチェッカーほどではない(一般的な範囲) | ◯ 露骨なNG表現は検知するが、Typolessほど特化していない |
| 読みやすさ・可読性の改善 | ◯ 冗長さや難解表現の指摘は一定レベル | ◎ 冗長・重複を減らし、テンポの良い文へ整えやすい | ◎ SEOライティング視点での読みやすさ調整に強い |
| 違和感のある語感の指摘 | ◯ 不自然な組み合わせは指摘 | ◎ ネイティブ感のある日本語へ近づける提案が多い | ◎ コピー的な言い回しも含め、ニュアンス調整に強い |
・精度重視なら Typoless、文脈の自然さ重視なら Shodo。
・SEO文脈やWeb文章なら 文賢 の可読性調整が最強。
・炎上リスク対策は Typoless が圧倒的に強い。
AIの質の比較
AIが提示する“言い換え”や“リライト”の品質は、文章の雰囲気を大きく左右します。このパートでは、提案型か自動書き換えか、言い換えの自然さ、説明可能AI(XAI)の有無、長文校正の安定性などを比較。Shodoは自然で軽快な提案、Typolessは安全性と正確さ重視、文賢は論理構造を整えながら読みやすさを高める提案が得意です。
AI提案の質の比較
| 項目 | Typoless | Shodo | 文賢 |
|---|---|---|---|
| 提案型 or 自動書き換え | 主にチェック+提案型(一括修正も可能) | 提案型校正。候補から選んで反映するスタイル | 提案型+AIアシスト。ユーザーが採用・修正を選択 |
| 言い換えの自然さ | ◯ 正しさ重視の堅めの言い換えが中心 | ◎ 会話的で自然な文体も含めて提案してくれる | ◎ 説明的・教育的な文体の言い換えに強い |
| 文章リライトの質 | ◯ 意味保持重視で安全寄りのリライト | ◎ 意図を残したままテンポよく整えるリライトが得意 | ◎ 構成や論理の通りをよくする提案が多い |
| Copilot/生成AIモード | 生成AIは限定的(校正中心) | 生成AIを活用した提案型校正を標準搭載 | AIアシスト機能で見出し案・言い換え等を提案 |
| 説明可能AI(XAI)の有無 | ◎ なぜ誤りかの説明が丁寧(新聞社の校正ロジック) | ◯ 提案意図は概ね理解しやすいが、XAI特化ではない | ◯ ルールとガイドラインに基づいた説明が多い |
| 長文への安定度 | ◎ 報告書・冊子などの長文を安定して処理 | ◯ 1記事単位なら十分実用レベル | ◎ 長めのWeb記事の校正・推敲に最適 |
・自然さとテンポ重視なら Shodo が最も快適。
・正しさ・安全性重視なら Typoless が安心。
・論理性・説明テキストの改善なら 文賢 が強い。
機能の比較
Word・Google Docs・PowerPoint・PDF・APIなど、文章を扱う現場は多様です。この機能比較では、「自分のワークフローにどれが一番馴染むか」を判断しやすいよう、各ツールの対応範囲を整理しました。PDFや冊子をそのまま校正したいならTypoless、Web記事中心ならShodoと文賢の軽さが魅力。組み込みや拡張性を重視する場合はAPI対応がカギになります。
機能の比較
| 項目 | Typoless | Shodo | 文賢 |
|---|---|---|---|
| Word連携 | ◯ 対応(アドイン) | ◎ 対応(アドイン) | △ ブラウザ中心(外部ツールで対応) |
| Google Docs連携 | ◯ 対応 | ◎ 対応 | △ 直接連携はなし(コピペ運用が基本) |
| PowerPoint対応 | ◎ プレミアム以上で対応 | △ 資料テキストはコピペ前提 | △ 同上 |
| PDF/OCR対応 | ◎ PDF/OCRに強く、冊子・レポートも直接校正可 | △ テキスト抽出後の校正が前提 | △ 同上 |
| ブラウザ拡張(Chrome等) | ◯ 対応(Webサービス上の文章もチェック) | △ 公式拡張は限定的 | △ 主にWebアプリ内で利用 |
| API連携 | ◎ APIプランあり(最大1,000万文字) | ◎ API100/500/1000プランでCMS連携が可能 | △ 公開情報ベースでは限定的(主にアプリ内利用) |
| 差分管理・履歴 | ◯ 校正前後の比較が可能 | ◎ 差分管理・共有リンク機能あり | ◎ 修正履歴やルールの蓄積を前提とした設計 |
| スコアリング・分析 | ◯ 読みやすさ等の指標表示あり | ◎ 文章分析機能で傾向を可視化 | ◎ Webライティング視点の分析・ガイドが充実 |
・PDFや資料校正なら Typoless の機能幅が最強。
・Web記事・ブログなら Shodo / 文賢 が軽快で扱いやすい。
・API連携は Shodo がもっとも明確で導入しやすい。
チーム運用の比較
チームで文章を扱う際は、個人利用とは比べものにならないほど運用フローが複雑になります。この比較では、権限管理・辞書共有・スタイルガイド・Slack連携・大規模導入実績など、“チーム全体で整える力”に焦点を当てました。文章品質を統一したい部署や制作会社にとって、どのツールが最も武器になるかを判断できます。
チーム・組織での運用比較
| 項目 | Typoless | Shodo | 文賢 |
|---|---|---|---|
| 権限管理 | ◎ エンタープライズでSAML認証・権限分離に対応 | ◎ ビジネスプランでロール/権限管理に対応 | ◯ 複数ライセンスでの運用を前提とした設計 |
| チーム辞書・ルール共有 | ◎ 自社辞書・禁止語などを共有可能 | ◯ 表記ゆれ設定やルール共有が可能(ビジネス) | ◎ 文賢の強み。辞書・ルールをチームで共通化しやすい |
| ガイドライン運用 | ◎ 新聞社基準をベースに社内ルールを上書き可 | ◯ 自社ルールを反映しながら運用可能 | ◎ スタイルガイドと連動しやすく、教育にも向く |
| Slack通知・連携 | △ 公式連携情報は限定的 | ◎ ビジネスプランでSlack通知に対応 | △ 主にアプリ内運用(連携は別設計が必要) |
| 大規模導入の実績 | ◎ 官公庁・大企業・教育機関などの実績多数 | ◯ PR TIMESや制作会社など中〜大規模で導入 | ◯ Web制作会社・メディアでの導入事例が中心 |
| ナレッジ・教育効果 | ◎ 校正ルールを通じて「正しい日本語」を学べる | ◎ 提案から「言い回しの引き出し」を増やせる | ◎ 文賢のガイドと合わせて“書く力”の底上げがしやすい |
・組織ガバナンスが重要なら Typoless。
・中小企業の実務運用なら Shodo が最も手軽で柔軟。
・文章ルール統一と教育効果は 文賢 が頭一つ抜けている。
セキュリティの比較
機密情報や社外秘の文章を扱う場合、校正精度以上に重要になるのがセキュリティです。このパートでは、データ保存の有無、AIモデル学習への利用方針、認証方式、専用クラウド対応などを比較しました。特に官公庁・大企業など厳しい要件が求められる環境では、TypolessとShodoが強力な選択肢になります。
セキュリティ・コンプライアンスの比較
| 項目 | Typoless | Shodo | 文賢 |
|---|---|---|---|
| データ保存 | ◎ 入力データは保存しない設計(ログ最小限) | ◎ 通信暗号化・保存は最小限。機密文書配慮の設計 | ◯ 保存ポリシーは公式情報に準拠(詳細は要確認) |
| モデル学習への利用 | ◎ 入力文はAI学習に利用しない方針を明記 | ◎ モデル学習には利用しない旨を明示 | ◯ 個人情報保護方針に準拠(詳細は最新の公式情報を要確認) |
| 認証・認証連携 | ◎ ISO/IEC 27001:2022認証/SAML認証対応(エンタープライズ) | ◯ IP制限/権限管理での制御が中心 | ◯ ID・パスワード管理が基本(SSOは別途要確認) |
| 専用環境(自社クラウド) | ◯ エンタープライズ契約で個別対応の可能性あり | ◎ エンタープライズで自社クラウド運用に対応 | △ 公開情報ベースでは標準環境が中心 |
・最高レベルの安全性を求めるなら Typoless。
・自社クラウド構築も含めた柔軟性なら Shodo。
・文賢は標準的なWebサービス運用にフィット。
料金の比較
実際の導入判断では「月いくらかかるのか」が最終的な決め手になることも多いです。この比較では個人向け料金、チーム向け料金、APIの価格帯、初期費用、無料トライアルの有無を整理しました。コスパ重視ならShodo、媒体品質を担保したい組織ならTypolessや文賢など、目的とのバランスで選びやすくなります。
料金・プランの比較(目安)
| 項目 | Typoless | Shodo | 文賢 |
|---|---|---|---|
| 個人向けプラン | スタンダード:2,200円/月 プレミアム:3,850円/月 +Plus:7,700円/月(税込) |
ベーシック:0円/月 プレミアム:1,000円/月(税込) |
初期費用:11,880円+ 月額:2,178円/月(税込) |
| チーム・法人向けプラン | エンタープライズ:24,750円〜/月(税込) ※ID数・機能により変動 |
ビジネス:2,000円/名/月(税込) エンタープライズ:個別見積り |
複数ライセンス割引あり(5ID〜/15ID〜など段階的) |
| APIプラン | 見積制/最大1,000万文字対応 | API100:100万文字〜/月 API1000:1,000万文字〜/月 |
API連携は個別相談レベル(公開情報ベース) |
| トライアル・初期費用 | 無料トライアルあり/初期費用なし | 14日間無料トライアルあり/初期費用なし | オンライン説明会経由でトライアルあり/初期費用 11,880円 |
※料金・プラン内容は変更される可能性があるため、最新情報は必ず各公式サイトをご確認ください。
・個人利用のコスパ最強は Shodo。
・組織の品質管理とガバナンスは Typoless が最適。
・Web制作チームでの実務運用は 文賢 が安定。
タイプ別おすすめAI校正ツール
校正ツールは「どれが一番良いか」ではなく、「誰に最適か」で選ぶのが失敗しないコツです。 Typoless・Shodo・文賢は、それぞれ得意領域や想定ユーザーが明確に異なります。 本パートでは、用途別に最適な1本を選べるよう、編集部が“タイプ別の最適解”を整理しました。 誤字脱字の厳格チェック、Web記事の読みやすさ向上、文脈理解による自然な校正、資料やPDFの校正、 さらにはチーム運用やAPI連携まで、目的別に迷わず判断できるマップになっています。
| タイプ | 最適なツール | 理由・特徴 |
|---|---|---|
| 誤字脱字・表記ゆれの“厳格チェック”が必要 | Typoless | 新聞社品質のルール辞書で、社会的リスクを最小化。 |
| 自然で読みやすい“文脈校正”がしたい | Shodo | 文脈理解・違和感のない提案が得意。個人・中小企業に最適。 |
| SEO記事・オウンドメディアの品質をそろえたい | 文賢 | 読みやすさ・構成改善・論理性など“Web文章”に強い。 |
| 資料・PDF・冊子など非Web文書の校正が多い | Typoless | PDF校正・OCR対応が優秀。統一基準で全社の内容を管理できる。 |
| 記事執筆〜校正をコスパ重視で行いたい | Shodo | 月1,000円で文脈校正・Docs/Word対応まで可能。 |
| チーム全体で“文章ルール”を統一したい | 文賢 or Typoless | 文賢=Web編集最強 / Typoless=コンプラ最強。 |
| 炎上リスク(差別・ジェンダー・政治)を避けたい | Typoless | 朝日新聞社基準で“差別表現検知”が最も強い。 |
| ITサービスにAI校正を“組み込みたい” | Shodo(API) | APIプラン明確。月100万〜1,000万文字で拡張性も高い。 |
| 編集に慣れていない人でも使いやすいツールが欲しい | Shodo | 提案が直感的で“押すだけで整う”初心者向けUI。 |
・精度・リスク管理を最優先する組織は「Typoless」が最適。
・読みやすさ・文脈理解を安く強化したいなら「Shodo」。
・Web編集・SEO記事の品質統一なら「文賢」が最も効果的。
どのAI校正ツールが最適?簡易診断チャート
校正ツールは「どれが一番優れているか」ではなく、「どの特性があなたの文章や環境に合っているか」で選ぶことが大切です。 この簡易診断チャートでは、誤字脱字の厳格さ、文脈の自然さ、SEO適性、PDF校正、チーム運用といった判断軸をもとに、 最適な1本を数ステップで判定できます。 迷ったときは、このチャートで“最初の1本”を選ぶと失敗しません。
A:誤字脱字・表記ゆれを“厳格に”直したい? → YES → Typoless / NO → Bへ
B:文章を“自然に読みやすく”したい? → YES → Shodo / NO → Cへ
C:SEO記事・Web文章を強化したい? → YES → 文賢 / NO → Dへ
D:PDF・冊子など非Web文書を扱う? → YES → Typoless / NO → Eへ
E:チームで文章基準を統一したい? → 文賢 または Typoless
・厳格さ→Typoless、自然さ→Shodo、Web文章→文賢が基本軸。
・文章用途と職種で最適解は大きく変わる。
・まずは“自分が何を重視したいか”を整理するのが成功の近道。
AI校正ツール選びのチェックリスト(編集部作成)
・文章の“種類”と“仕事の流れ”から逆算して選ぶのが重要。
・コンプラ要件・運用ルールはツールごとに大きく差がある。
・選ぶ前にチェックリストで条件を整理するとミスマッチが防げる。
- 誤字脱字の“厳格さ”が必要か
- 文章の自然さ・読みやすさを優先したいか
- 炎上リスク(差別・ジェンダーなど)を避けたいか
- 社内の文章基準を統一したいか
- Word/Google Docs で使いたいか
- PDF・冊子など非Web文書も校正したいか
- チーム利用で権限管理が必要か
- 自社サービスにAI校正を組み込みたいか(API)
- 月額いくらまで許容できるか(個人/チーム)
- 編集経験が浅い人でも使いやすいUIが必要か
初めて校正ツールを導入するときは、機能表だけでは判断しにくいものです。 このチェックリストは、「何を基準に選ぶべきか」を編集部視点で整理したもの。 文書の種類、コンプラ要件、チーム運用、APIの必要性、UIのわかりやすさなど、 導入後の“使いこなし”まで含めて比較できるよう設計しています。 5分で判断軸が明確になるため、失敗しにくい選び方ができます。
文章タイプ別おすすめ(ビジネス文書/SEO/PR/社内資料)
文章のジャンルによって、必要な校正の方向性は大きく変わります。 例えば、ビジネス文書では“伝わりやすさ”、SEO記事では“読みやすさ+構成の筋”、PR文では“正確さと炎上回避”が重視されます。 この一覧表では、文章タイプごとに最も相性の良い校正ツールを整理しました。 自分の仕事・業務内容に近い項目を確認することで、最短で最適解にたどり着くことができます。
- 誤字脱字の“厳格さ”が必要か
- 文章の自然さ・読みやすさを優先したいか
- 炎上リスク(差別・ジェンダーなど)を避けたいか
- 社内の文章基準を統一したいか
- Word/Google Docs で使いたいか
- PDF・冊子など非Web文書も校正したいか
- チーム利用で権限管理が必要か
- 自社サービスにAI校正を組み込みたいか(API)
- 月額いくらまで許容できるか(個人/チーム)
- 編集経験が浅い人でも使いやすいUIが必要か
・文章ジャンルで“求める校正の質”は大きく変わる。
・ビジネス→Shodo、SEO→文賢、PR→Typolessが基本軸。
・まずは自分が扱う文章の特性を確認するのがベスト。
導入前に見るべき失敗しやすいポイント表
・“用途”と“運用フロー”を無視した選択は失敗の原因。
・PDF・チーム運用はツール差が大きく要確認。
・導入後の教育・ルール整備が効果を左右する。
- “自然さ”と“正確さ”はトレードオフになりやすい
- 無料版は文字数・機能が大幅に制限されることが多い
- AIが正しく判断できない専門用語・慣用表現がある
- 組織導入は「権限管理」と「辞書共有」が必須
- PDFや紙資料の校正はツールによって得意・不得意が分かれる
- AIの提案を“そのまま採用”すると文体が崩れる場合がある
- 炎上リスクはツールでは完全には防げない
- 導入後の教育・運用ルールがないと効果が半減する
校正ツールの導入でよくある失敗は、「機能の強さ」だけを見て選んでしまうことです。 実際には、文章ジャンル・チームの運用フロー・権限管理・PDF対応など、 現場の運用に直結するポイントが見落とされやすく、導入後に“思っていたのと違う”となるケースが多々あります。 このリストを事前に確認しておくことで、ミスマッチを避け、導入効果を最大化できます。
AIの限界(AI校正ができない領域のまとめ)
AI校正は非常に便利ですが、「万能」ではありません。 文脈の裏にある意図、読者の感情、ブランドトーン、専門分野の細かなニュアンスなど、 人間の編集力が必要な領域はまだ多く残っています。 このパートでは、AIが苦手とする箇所を明確にし、どこまでAIに任せて、どこから人が介入すべきかを整理しています。
- 「文脈の裏にある意図」を完全には理解できない
- 専門用語・固有表現・業界特有の言い回しに弱い
- 文体・キャラクター性・ブランドトーンの維持が難しい
- 文章の“論理展開”や“ストーリー性”は人間の編集力に劣る
- 正しい表現でも“違和感があるか”までは判断できない
- 炎上リスクは最終的に人間の判断が必須
- 長文になるほど不均一な提案が混じることがある
- 「正しいが読みづらい」文章の改善は苦手
・AIは“意図”や“感情”の理解がまだ不完全。
・専門領域・固有表現は人のチェックが必須。
・最適解は「AI×人」のハイブリッド運用。
気になるツールがあれば、まずは公式サイトとAI Workstyle Labの解説記事をセットでチェックしてみてください。 「機能の概要 → 実務での使いどころ」の順に見ると、自分の環境に合うかどうか判断しやすくなります。
文脈を読み取って自然な日本語へ整える「提案型AI校正」。個人ライターから中小企業の広報・制作チームまで、 コスパ良く“読みやすさ”を底上げしたい人におすすめです。
朝日新聞社の10万件ルールをもとに、誤表記と炎上リスクから「言葉の信頼」を守る校正ツール。 公的文書・IR・プレスリリースなど、社会的信頼が重要な文章に向いています。
ウェブライダーの編集ノウハウを凝縮した、Webライティングに強い校正・推敲ツール。 SEO記事・オウンドメディア・教材など、「伝わる文章」をチームで育てたいときの本命候補です。
※料金・機能は執筆時点の情報をもとに記載しています。最新情報は必ず各公式サイトでご確認ください。
番外編|ChatGPTで文章校正するときのポイントまとめ
ChatGPTは文章生成だけでなく、文章校正にも活用できます。 ただし、専門の校正ツールとは得意・不得意が異なるため、 “どこまで任せられるか”を理解して使うことが重要です。 以下では、ChatGPTでできること・注意点・リスクを プロ視点で整理した番外編としてまとめています。
| カテゴリ | 内容 |
|---|---|
| できること | ・文章全体の流れ・論理性・構成を改善 ・読みやすい文体への調整(丁寧語・語尾・冗長削減) ・表現の自然さ、比喩・言い換え提案 ・要約・段落整理・段階的な推敲 ・プロンプト次第で“文体を揃える”など高度な整形 |
| 注意点 | ・正しい情報と“それっぽい表現”を混同することがある ・校正基準(新聞・広報・業界ルール)が一貫しない ・固有名詞や専門語は変換ミスが起きやすい ・プロンプトの指示が曖昧だと仕上がりが不安定 ・文賢やTypolessのような「辞書精度」は持たない |
| リスク | ・意図の改変(勝手に文章を変える) ・誤った推測による“意味のずれ” ・炎上リスク表現の検知は不完全 ・誤字脱字の抜け漏れが発生 ・校正結果に一貫性が出ない(回ごとに変わる) → 専門の校正DX用途には不向き |
・ChatGPTは“読みやすさ調整”や“文章の流れの改善”が得意。
・誤字脱字・表記ゆれ・炎上防止などの“厳密校正”は苦手。
・最適解は「AI生成&推敲はChatGPT → 校正は専門ツール」。
まとめ
AI文章校正ツールは、いまやライター・企業・編集チームにとって欠かせない存在です。しかし「どれが一番優れているか」ではなく、「どの文章に、どのシーンで、どの精度が必要か」によって最適なツールは変わります。
Typolessは厳密なルール・炎上防止に強く、Shodoは文脈理解による自然で読みやすい文章を作るのが得意。
文賢はSEO・Web文章向けの推敲に最適で、ChatGPTは構成整理や表現の改善など、“文章の下地づくり”に力を発揮します。
重要なのは、これらを対立軸で考えるのではなく、AIと人間、そして複数ツールを組み合わせることで文章の質を最大化できる点です。
本記事を通して、自分の文章環境に合う最適解が明確になり、毎日の制作・執筆がよりスムーズで質の高いものになれば幸いです。
AI校正ツールに関するよくある質問|FAQ
Q1. 初心者が最初に試すなら、どの校正ツールがおすすめですか?
文章校正に慣れていない方には、直感的なUIで提案がわかりやすい Shodo をおすすめします。ブラウザ上で完結し、GoogleドキュメントやWordとも連携できるため、 「書く→整える」の一連の流れをスムーズに体験できます。
Q2. ビジネス文書(報告書・企画書)にはどのツールが向いていますか?
ビジネス文書では「伝わりやすさ」と「文体の適切さ」が重要です。 自然な日本語表現に整えたい場合は Shodo、 社内ルールやコンプライアンスを重視する場合は Typoless が候補になります。
Q3. SEO記事やオウンドメディアの文章にはどのツールが相性が良いですか?
SEO記事やオウンドメディアでは「読みやすさ」「論理構成」「読者目線」が重要です。 Web文章に特化した辞書とチェック観点を持つ 文賢 がもっとも相性が良く、 Shodoを併用すると文脈レベルの自然さもカバーできます。
Q4. 無料で試せるプランはありますか?
記事執筆時点では、Shodo・Typoless・文賢 すべてに 無料トライアルまたはお試し利用の仕組みがあります(文字数・機能は制限あり)。 料金や制限内容は変更される可能性があるため、必ず各公式サイトで最新情報をご確認ください。
Q5. ChatGPTだけで文章校正は完結できますか?
ChatGPTは構成整理や表現の改善には力を発揮しますが、誤字脱字・表記ゆれ・炎上リスク検知など、 「厳密な校正」は専門ツールに劣ります。 理想は、ChatGPTで下地づくり → 専門ツールで最終チェック というハイブリッド運用です。
Q6. 小規模チームや制作会社で導入するなら、どれを優先すべきですか?
Web制作・コンテンツ制作が中心なら 文賢+Shodo の組み合わせが現実的です。 文賢で記事全体の設計やトーンを整え、Shodoで文脈レベルの自然さを仕上げると、 チーム全体の文章品質を底上げしやすくなります。
Q7. 官公庁・金融・大企業など、セキュリティ要件が厳しい場合は?
セキュリティ要件が厳しい環境では、データの扱い・IP制限・専用環境・契約形態が重要です。 特に Typoless と Shodo(エンタープライズ・自社クラウド対応) は、 こうしたニーズに対応しやすい設計です。詳細は必ず各社の公式資料でご確認ください。
Q8. PDFや冊子、既存資料の校正をしたい場合はどのツールがいいですか?
PDF・冊子・紙資料などの校正には、Typoless の対応範囲がもっとも広く、 OCRやレイアウトを含むチェックに強みがあります。 Webテキスト中心であれば、Shodoや文賢の方が軽快に使えるケースも多いです。
Q9. 校正ツール同士を組み合わせて使うメリットはありますか?
あります。例えば、ChatGPTで文章案を整え → Shodoで文脈校正 → Typolessでリスクチェック のように組み合わせると、「読みやすさ」と「正確さ」と「安全性」をバランス良く担保できます。 1本で完璧を目指すより、役割分担を明確にする方が効果的です。
Q10. どのツールを選ぶか迷ったとき、最初に確認すべきポイントは?
まずは、①どんな文章を扱うか(ビジネス/SEO/PR/社内資料など)、 ②個人利用かチーム導入か、 ③どこまでコンプラ・リスク対策が必要か の3点を整理しましょう。 そのうえで、本記事の「タイプ別おすすめ表」と「簡易診断チャート」を合わせて見ると、 自分にとっての最適解が見えやすくなります。
関連記事|AI文章校正ツール
- Typoless(タイポレス)完全ガイド|料金・使い方・評判・朝日新聞のAI校正DXを徹底解説
- 文賢(ブンケン)完全ガイド|AIが“書く力”を支える「共創型校正ツール」
- Shodo(ショドー)完全ガイド|AIが日本語を磨く「提案型校正クラウド」
参考・引用元一覧
- 文賢公式サイト(株式会社ウェブライダー) https://rider-store.jp/bun-ken/
- 文賢ヘルプセンター https://help.bun-ken.net/
- 文賢マガジン(導入事例・公式ブログ) https://magazine.bun-ken.net/
- Webライダー公式サイト https://web-rider.jp/
- キャリアデザインLAB|【WILL】AI×webライティングは副業初心者に最適 https://careerdesign-lab.net/side-business/will-ai-writing/
- Shodo(ショドー)公式サイト https://shodo.ink/
- Shodo公式サイト|料金プランページ https://shodo.ink/pricing/
- Shodoプライバシーポリシー(株式会社ゼンプロダクツ) https://shodo.ink/privacy
- 朝日新聞社 公式サイト|Typoless(タイポレス) https://typoless.asahi.com/
- Typoless公式ニュース・お知らせ一覧 https://typoless.asahi.com/news