日本精工株式会社(NSK)は、AIロボティクス企業である株式会社アールティ(RT社)と業務提携契約を締結し、さらにRT社の株式を取得して議決権の3分の1超を保有する株主となったことを発表しました。この戦略的投資と提携は、両社の強みを融合し、人手不足といった社会課題をAI・ロボット技術で解決することを目指すものです。

提携の背景と目的
NSKは、長年にわたり培ってきたトライボロジー(摩擦・摩耗・潤滑の科学)や解析技術、そしてベアリングや直動製品といった製品技術を基盤としています。一方、RT社はヒューマノイドロボットをはじめとする「人と柔軟に協調して作業するロボット」の開発・社会実装における先駆企業です。
この提携により、RT社が有する先進的なAI・ロボット技術とNSKの技術を融合させることで、より高付加価値なロボット製品・サービスを開発・提供することが可能になります。両社は、製造業やサービス業が直面する人手不足という社会課題をAI・ロボット技術で解決し、「人と共存するロボット社会の実現」に向けた取り組みを本格化させていく方針です。
株式会社アールティ(RT社)について
RT社は2005年の創業以来、「Life with Robot®」「Work with Robot®」を理念に掲げ、人とロボットが共に働き、共に生きる社会の実現を目指してきました。同社は、ヒューマノイドロボットや四足歩行ロボットなど独自のAIロボット開発において、エンボディードAI(ロボットが身体を通じて現実世界と相互作用しながら学習し、知能を発達させる概念)やフィジカルAI(機械が現実世界を理解して動作するために用いられる人工知能)の両面から、AIとハードウェアを融合する技術を強みとしています。
また、ROS(Robot Operating System:ロボット開発のためのオープンソースソフトウェアフレームワーク)をはじめとする先端ソフトウェア技術にも強みを持ち、日本におけるロボット基盤技術の普及をリードしています。研究開発から社会実装、さらには教育事業を通じて次世代の人材育成にも貢献している企業です。

- RT社ウェブサイト: https://rt-net.jp/
日本精工株式会社(NSK)について
NSKは1916年に日本で初めて軸受(ベアリング)を生産して以来、100年以上にわたり、軸受や自動車部品、精機製品などの革新的な製品・技術を生み出し、世界の産業発展を支えてきました。現在は約30ヶ国に拠点を持ち、軸受分野で世界第3位、ボールねじなどにおいても世界をリードするグローバル企業です。
企業理念として「MOTION & CONTROL™を通じて円滑で安全な社会に貢献し、地球環境の保全をめざす」ことを掲げ、2026年に向けたビジョン「あたらしい動きをつくる。」のもと、社会への貢献と企業の発展の両立を目指しています。

- NSKウェブサイト: https://www.nsk.com/jp-ja/
業務提携契約の主な内容
今回の業務提携契約には、以下の具体的な内容が含まれています。
-
国産四足歩行ロボットの実用化に向けた協業
-
製造業向けヒューマノイドロボットの社会実装に向けた共同開発および協業
-
AI/ハードウェア/ソフトウェア各種要素技術の共同研究と開発
-
両社技術・営業人材の交流を通じた、提案力の強化と市場開拓
AI Workstyle Lab編集部の解説
今回の日本精工とアールティの提携は、AIロボットの社会実装を加速させる上で非常に重要な意味を持ちます。特に注目すべきは、両社の持つ異なる強みが補完し合う点です。
RT社の持つ「フィジカルAI」や「エンボディードAI」といった最先端のAIロボット技術は、現実世界でロボットが自律的に学習し、人や環境と柔軟に協調するための基盤となります。これにNSKが長年培ってきた精密な機械要素技術、例えば摩擦を低減し動きを滑らかにするトライボロジー技術や高精度なベアリング、直動製品などが加わることで、ロボットの耐久性、精度、そして効率が飛躍的に向上することが期待されます。
これは、単にロボットを動かすだけでなく、より安全で信頼性の高い、そして何よりも「実用的な」ロボットを現場に導入するための大きな一歩と言えるでしょう。製造業における複雑な組み立て作業や、サービス業でのきめ細やかな顧客対応など、これまで人間にしかできなかった作業をロボットが担う可能性が広がります。AIを仕事で活用する視点で見れば、ロボットが定型業務だけでなく、より高度な判断を伴う作業を代替することで、人間はより創造的で戦略的な業務に集中できるようになるはずです。将来的には、AIロボットが私たちの働き方を根本から変革し、新たなワークスタイルを創出する可能性を秘めていると言えます。
今後の展望
NSKは本提携を契機に、ロボット事業への取り組みを本格化させ、製造業やサービス業における人手不足という社会課題に対し、AI・ロボット技術で解決策を提供していく方針です。両社の協業は、「人と共存するロボット社会の実現」に向けた具体的なステップとなるでしょう。
「AIニュースは追っているけど、何から学べばいいか分からない…」 そんな初心者向けに、編集部が本当におすすめできる無料AIセミナーを厳選しました。
- 完全無料で参加できるAIセミナーだけを厳選
- ChatGPT・Geminiを基礎から体系的に学べる
- 比較しやすく、あなたに合う講座が一目で分かる
ChatGPTなどの生成AIを使いこなして、仕事・収入・時間の安定につながるスキルを身につけませんか?
AI Workstyle LabのAIニュースをチェックしているあなたは、すでに一歩リードしている側です。あとは、 実務で使える生成AIスキルを身につければ、「知っている」から「成果を出せる」状態へ一気に飛べます。
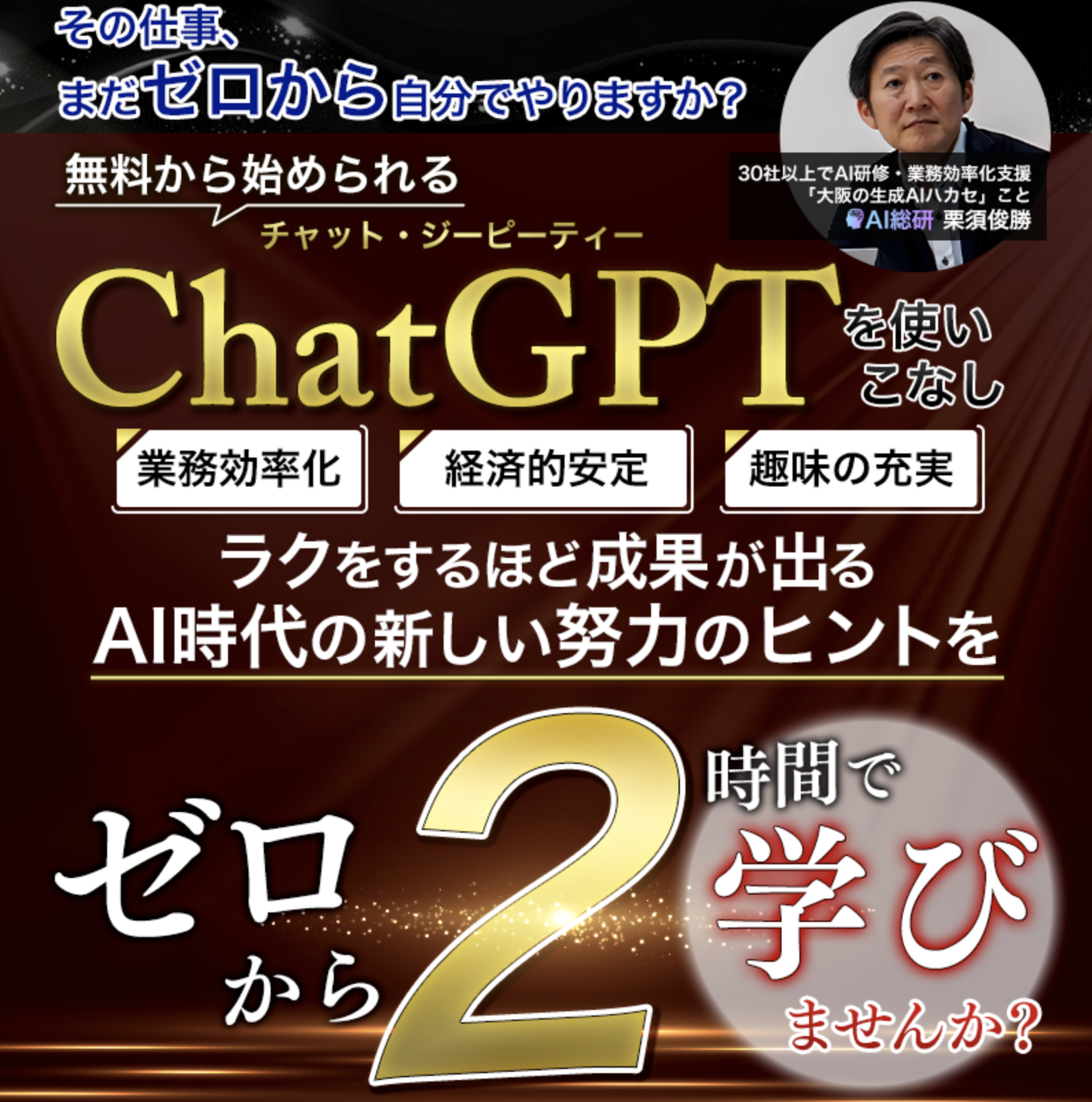
講師:栗須俊勝(AI総研)
30社以上にAI研修・業務効率化支援を提供。“大阪の生成AIハカセ”として企業DXを牽引しています。
- 日々の業務を30〜70%時短する、実務直結の生成AI活用法を体系的に学べる
- 副業・本業どちらにも活かせる、AI時代の「稼ぐためのスキルセット」を習得
- 文章・画像・資料作成など、仕事も趣味もラクになる汎用的なAIスキルが身につく
ニュースを読むだけで終わらせず、
「明日から成果が変わるAIスキル」を一緒に身につけましょう。
本記事は、各社の公式発表および公開情報を基に、AI Workstyle Lab編集部が 事実確認・再構成を行い作成しています。一次情報の内容は編集部にて確認し、 CoWriter(AI自動生成システム)で速報性を高めつつ、最終的な編集プロセスを経て公開しています。


