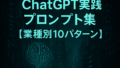AIライティングは「文章を自動生成する段階」から、「構成を設計する時代」へ進化しています。その象徴がTranscope(トランスコープ)。
SEO分析・キーワード設計・構成づくりまでAIが担い、下書き作成の常識を大きく刷新します。リサーチから執筆までを一気通貫で効率化したい人に最適の実務AIツールです。
- Transcope(トランスコープ)の基本概要と特徴
- Transcope(トランスコープ)のGPT-4/OpenAI o1を使った生成の仕組み
- Transcope(トランスコープ)の競合分析・キーワード分析・リライト機能の実力
- Transcope(トランスコープ)の使い方(ドキュメント/コンテンツ生成)
- 実際の出力とプロ添削による改善ポイント
- Transcope(トランスコープ)の料金プラン・導入補助金情報
- Transcope(トランスコープ)活用時の注意点・向いている人の特徴
- はじめに|AIが書く工程を進化させる時代へ
- 第1章 Transcope(トランスコープ)とは|SEO×AIライティングの融合ツール
- 第2章 Transcope(トランスコープ)の主な機能とできること
- 第3章 Transcope(トランスコープ)の実際の使い方(ドキュメント/コンテンツ生成)
- 第4章 Transcope(トランスコープ)の料金プランと補助金対応(IT導入補助金対象)
- 第5章 AI記事添削から学ぶ「Transcope(トランスコープ)の得意・不得意」
- 第6章 Transcope(トランスコープ)活用メリットと注意点
- 第7章 Transcope(トランスコープ)はどんな人に向いているか/向かないか
- 第8章 AIライティングの未来を描く:人とAIの共創プロセス
- 第9章 Transcope(トランスコープ)の口コミ・評判レビュー
- 編集部コメント|AIが書く力を支える時代に
- よくある質問(Q&A)
- AIライティングツールに関する関連記事
- 記事引用元・参考元
- ChatGPTで実現する再現性のあるSEOライティング設計
はじめに|AIが書く工程を進化させる時代へ
AIライティングが「文章を自動生成する時代」から、「構成を設計する時代」へと移り変わっています。
その進化を象徴するツールが、Transcope(トランスコープ)です。
単なる文章生成ではなく、「SEO設計・キーワード分析・構成づくり」までを自動化。
AIが構成力を持つことで、「書けるAI」という新たなステージに突入しました。
AI Workstyle Lab編集部がShodoを通して見た「整えるAI」の次に位置づけられるのが、この構成を描くAI──Transcope(トランスコープ)です。
SEO記事の下書きづくりから、競合分析、さらには音声文字起こしまで。
従来分断されていたプロセスをひとつのプラットフォームに統合することで、「リサーチから執筆までをAIで完結させる」という新しいワークフローを実現しています。
Transcopeは、キーワード分析・構成作成・文章生成までをAIが一括で行うSEO特化のライティングツール。 検索意図に沿った記事構成を自動で作れるため、記事品質を保ちながら制作時間を大幅に短縮できます。
▶ Transcopeの詳細を見る第1章 Transcope(トランスコープ)とは|SEO×AIライティングの融合ツール
1-1. Transcope(トランスコープ)の開発背景と基本理念
Transcope(トランスコープ)は、シュアモル株式会社が開発した日本発のAIライティングツールです。
「誰でもSEO記事を効率的に制作できる環境をつくる」ことを目的に開発され、
導入ユーザーの平均アクセス数を2.13倍まで引き上げたという実績もあります。
Transcope(トランスコープ)の特徴を一言で表すなら、
AIがSEO設計を理解し、構成と文章を同時に作るツール。
Transcope(トランスコープ)は文章生成だけでなく、競合分析・キーワード分析・順位追跡といったSEO要素をAIが自動で実行。
ライター・編集者・マーケターの思考の起点として活用できる設計になっています。
1-2. Transcope(トランスコープ)の進化したAIエンジン「OpenAI o1」とGPT-4
Transcope(トランスコープ)には、OpenAI社の最新モデル「o1」が搭載されており、一部のモードではGPT-4も併用されています。
これにより、文脈の自然さ・トーンの統一性・SEOキーワードの最適配置が飛躍的に向上。
- 日本語の文体・語感の自然さ(AIらしい違和感の軽減)
- 指定したキーワードの自然挿入(無理のないSEOライティング)
- 文脈に基づく段落構成(読みやすさ・論理性の両立)
Transcope(トランスコープ)は単なる自動生成ではなく、「文脈を理解した構成づくり」ができる点が、他のAIツールと大きく異なります。
1-3. Transcope(トランスコープ)の競合との差別化ポイント
多くのAIライティングツールが文章を作ることにフォーカスしている中で、Transcope(トランスコープ)は記事全体の設計を作ることに重きを置いています。
比較してみましょう。
| 項目 | ChatGPT | Transcope(トランスコープ) |
|---|---|---|
| モデル | GPT-4 | GPT-4+o1(SEO最適化チューニング) |
| 目的 | 汎用文章生成 | SEO構成+競合分析+執筆 |
| 機能範囲 | プロンプト依存 | 構成提案・順位分析・記事出力 |
| 翻訳/要約 | ○ | ○+自社情報学習対応 |
| コピーチェック/薬機法チェック | × | ○ |
| 専門記事向き | 要カスタム | 学習データ登録で最適化可能 |
AIが構成を描き、人間が整える──。
Transcope(トランスコープ)は、まさに「AIと人の共創」を前提に設計された実務AIです。
Transcopeは、キーワード分析・構成作成・文章生成までをAIが一括で行うSEO特化のライティングツール。 検索意図に沿った記事構成を自動で作れるため、記事品質を保ちながら制作時間を大幅に短縮できます。
▶ Transcopeの詳細を見る第2章 Transcope(トランスコープ)の主な機能とできること
Transcope(トランスコープ)の魅力は、SEOライティングに必要な機能が一括で完結する点にあります。
ここでは、編集部が注目した主要機能をピックアップして紹介します。
2-1. Transcope(トランスコープ)の競合分析・キーワード分析
SEO記事制作で最も時間がかかる「リサーチ」を自動化。
Transcope(トランスコープ)では上位記事を分析し、使用キーワード・出現頻度・見出し構成をAIが解析します。
分析結果は「利用ワード」「流入ワード」「見出し」タブに整理され、上位記事がどのようにテーマを展開しているかが一目でわかります。
これにより、人が考える構成の前にAIが提案するという逆転的な執筆体験を実現しました。
2-2. Transcope(トランスコープ)のコンテンツ生成機能(多入力対応)
Transcope(トランスコープ)では、以下の多彩な入力方法から文章を生成できます。
- キーワード入力(フリーテキスト)
- URL解析:参考記事を指定して要約・リライト
- Google検索結果分析
- 画像/CSVファイルアップロード
- 自社情報(CSV学習)による専門記事生成
この柔軟性が、他のAIツールにはない強み。
「1テーマ=1記事」だけでなく、「複数商品を比較する記事」「FAQまとめ」などにも応用できます。
2-3. Transcope(トランスコープ)の自社データ学習機能(ナレッジ連携)
Transcope(トランスコープ)は無料プランでも10,000文字、有料プランでは最大100万文字まで、自社の過去記事・用語集・FAQをAIに学習させることが可能です。
たとえば、企業サイトなら「ブランドトーン」「専門用語」を学習させておけば、AIが自然に社内文体で記事を生成してくれる。
「企業専用AIライター」として活用できる仕組みです。
2-4. Transcope(トランスコープ)の文章チェック機能(品質+法令対応)
Transcope(トランスコープ)には以下の自動チェックが搭載されています。
- コピーコンテンツチェック
- 薬機法チェック(医療・美容系コンテンツ向け)
- ファクトチェック(根拠・真偽確認)
これにより、SEOだけでなくコンプライアンスを意識した執筆が可能になります。
特に薬機法チェックを標準搭載している点は、医療・美容分野の企業にとって大きな安心材料です。
2-5. Transcope(トランスコープ)の音声文字起こし・AI校正
Transcope(トランスコープ)では音声ファイルの文字起こしが可能で、5分までならどのプランでも無料で利用できます。
録音データをアップロードするだけでAIがテキスト化し、トーン指定(例:「落ち着いた雰囲気」「親しみやすい雰囲気」など)で整文。
会議議事録や取材原稿などにも活用可能です。
Transcopeは、キーワード分析・構成作成・文章生成までをAIが一括で行うSEO特化のライティングツール。 検索意図に沿った記事構成を自動で作れるため、記事品質を保ちながら制作時間を大幅に短縮できます。
▶ Transcopeの詳細を見る第3章 Transcope(トランスコープ)の実際の使い方(ドキュメント/コンテンツ生成)
Transcope(トランスコープ)は「コンテンツ生成」と「ドキュメント」の2モードを使い分けます。
ここからは、それぞれの具体的な使い方を紹介します。
3-1. Transcope(トランスコープ)のコンテンツ生成モード
Transcope(トランスコープ)の「コンテンツ生成」は、短文またはセクション単位の記事をAIが生成する機能。
基本操作は以下の通りです。
- 生成方法(キーワード/URL/画像/CSV)を選択
- 雰囲気・文字数・言語(日本語/英語/中国語)を指定
- 「生成」ボタンをクリック
- 複数の文章案を比較・選択
このモードは、商品説明・キャッチコピー・部分リライトなど、部分生成+構成案作成に最適です。
3-2. Transcope(トランスコープ)のドキュメントモード
Transcope(トランスコープ)の「ドキュメント」は、長文記事を自動構成から生成まで行うモードです。
AIがキーワードをもとに競合分析を実施し、タイトル案・見出し案を提案。
そのまま「構成を保存 → 文章生成」を押すだけで、数千字の記事を自動作成できます。
- キーワードまたはURLを入力して分析開始
- AIがタイトル・見出し構成を提示
- 見出しを取捨選択・修正
- 文章トーンや雰囲気を指定
- 「文章を生成する」で出力
- 内容を確認・リライト・公開準備
AIが生成した構成はSEO観点で非常に合理的ですが、同時に人の感性で磨く余地も残されています。
タイトルの具体性、見出しのリズム、読者への共感。
ここに人の編集が加わることで、記事は一気に完成度を増します。
第4章 Transcope(トランスコープ)の料金プランと補助金対応(IT導入補助金対象)
Transcope(トランスコープ)は無料プランを含む4つの料金体系を採用しています。
すべて税込・月額制で、1か月単位で契約・解約が可能です。
| プラン | 料金/月 | 月間文字数 | 主な機能 |
|---|---|---|---|
| Free | 無料 | 4,000文字 | 1週間利用・分析3回・キーワード選定3回 |
| Basic | ¥11,000 | 50,000文字 | 全機能利用・順位調査10ワード・内部リンク提案3回 |
| Pro | ¥38,500 | 250,000文字 | 内部リンク提案無制限・分析無制限 |
| Enterprise | ¥66,000 | 600,000文字 | 検索順位1,000ワード・API連携可 |
さらに、以下のオプションで柔軟な拡張も可能です。
- 文字数追加(20,000文字)¥3,080〜¥4,400
- 学習データ追加(100万文字)¥11,000
- 文字起こし追加(10時間)¥3,300
また、Transcope(トランスコープ)はIT導入補助金の対象ツールとして登録されており、中小企業や個人事業主でも導入コストを抑えやすい点も魅力です。
Transcopeは、キーワード分析・構成作成・文章生成までをAIが一括で行うSEO特化のライティングツール。 検索意図に沿った記事構成を自動で作れるため、記事品質を保ちながら制作時間を大幅に短縮できます。
▶ Transcopeの詳細を見る第5章 AI記事添削から学ぶ「Transcope(トランスコープ)の得意・不得意」
株式会社なかみによる実験では、「食べてないのに痩せない」というSEOテーマで
Transcope(トランスコープ)を使い、AIが生成した記事をプロのライターが添削しました。
結果として見えてきたのは、AIの「構成力の高さ」と感情表現の弱さの対比です。
- 検索意図に基づいた見出し設計
- キーワードの自然な配置
- 段落構成の論理性
- 無駄のない文量と可読性
- 共感を誘う語り口(読者に寄り添うトーン)
- 具体性・感情表現・ストーリーの不足
- 文章のテンポとリズム(機械的になりやすい)
添削による改善例では、たとえば次のような変化が生まれました。
この違いこそが、人とAIの共創領域。
Transcope(トランスコープ)は、構成をAIが描き、感情を人が添えるという理想的な分業モデルを体現しています。
第6章 Transcope(トランスコープ)活用メリットと注意点
6-1. Transcope(トランスコープ)活用メリット:SEO設計から執筆までを統合
- 競合分析・キーワード調査・構成作成・執筆を一括完結
- 複数ツールを併用していた工程を1つに集約
- 構成の質が上がり、リライト作業が効率化
SEO担当者・ブロガー・編集者のいずれにとっても、「調べる時間をAIに預けて、考える時間を取り戻す」ツールといえます。
6-2. Transcope(トランスコープ)活用の注意点:AI出力の限界を理解する
Transcope(トランスコープ)を効果的に使うためには、以下の3点に注意しましょう。
- リライトは必須:GPT-4でも文体の硬さ・語尾の単調さは残る
- ファクトチェックが重要:誤情報が含まれる可能性あり
- コピーチェック推奨:学習データ由来の類似表現が発生する場合あり
AIを代筆者ではなく、「共同編集者」として扱うこと。
これがTranscopeを最大限に活かすポイントです。
第7章 Transcope(トランスコープ)はどんな人に向いているか/向かないか
- SEO記事を自力で作りたい個人・企業
- 構成から執筆までをワンストップで完結したい人
- 外注コストを削減したいブロガー・マーケター
- 社内でナレッジを学習させたいチーム
- 文章の細部修正を面倒に感じる人
- 完全自動生成で記事を量産したい人
- AI出力をそのまま公開するスタイルを求める人
Transcope(トランスコープ)は、人の手によって磨かれる前提のAIツールです。
自分の意図を反映させたい人にこそ、最も向いています。
第8章 AIライティングの未来を描く:人とAIの共創プロセス
AIが書く構成を、人が編集する。
このプロセスが、今後のコンテンツ制作の主流になっていくでしょう。
Transcope(トランスコープ)は、「自動化」と「人の創意」を両立する中間地点に立っています。
AIは文章を生み出すのではなく、「人の構想を補助」する。
そこに生まれるのは、人間だけでは届かなかった思考の深さです。
AIが示す構成の骨格をベースに、感情・共感・ストーリーを人が重ねる──
それがAI Workstyle Labが提唱する「共創型ライティング」の未来です。
第9章 Transcope(トランスコープ)の口コミ・評判レビュー
Transcope(トランスコープ)は、SEO構成とAI生成を統合した実務型ライティングツールとして注目を集めています。
実際のユーザーからは「競合分析の精度が高い」「構成づくりの時短につながる」といった声が多く見られました。
| 評価ポイント | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 競合分析の精度 | 競合記事の見出しや使用キーワードを自動抽出でき、SEO設計が圧倒的に楽になる。 | カメコンパス |
| 構成作成の時短 | 記事構成が短時間で整い、月1本分の作業量がまるごと時短できた。 | サクフリ編集部 |
| 使いやすさ・実務向け | SEO構成と生成を統合しているため実務で使いやすいと評価されている。 | 総合評価 |
| 無料プランの制限 | 無料プランの機能制限が多く、有料プランは比較的高め。 | タツキングブログ |
| 生成文章の品質 | 生成文の手直しやファクトチェックは必須で、完全自動生成には向かない。 | ぎょぎょライティング |
口コミ・評判|良い声
「Transcopeを使うと、記事構成が短時間で整い、月1本分の作業がまるごと時短できた」(出典:サクフリ)
「競合記事の見出しや使用キーワードを自動で抽出できるため、SEO設計が圧倒的に楽になる」(出典:カメコンパス)
口コミ・評判|注意点
「無料プランの制限が多く、有料プランは比較的高め」(出典:タツキングブログ)
「生成文の手直しやファクトチェックは必須」(出典:ぎょぎょライティング)
まとめ
Transcope(トランスコープ)は完全自動生成を求める人よりも、AIと共に考える編集者・マーケター向けのツールといえるでしょう。
総じて、Transcope(トランスコープ)は「AIが構成を描き、人が感情を添える」共創型のライティング体験を求める人にとって最適な選択肢です。
Transcopeは、キーワード分析・構成作成・文章生成までをAIが一括で行うSEO特化のライティングツール。 検索意図に沿った記事構成を自動で作れるため、記事品質を保ちながら制作時間を大幅に短縮できます。
▶ Transcopeの詳細を見る編集部コメント|AIが書く力を支える時代に
Shodoが「文章を磨くAI」なら、Transcope(トランスコープ)は「文章を描くAI」。
両者を組み合わせることで、AIライティングの全工程が完成します。
執筆の前に、構成を設計する。
執筆の後に、表現を整える。
この往復のなかで、AIは思考のパートナーになっていく。
AI Workstyle Labはこれからも、「AIが人を拡張する」実践例を追い続けます。
あなたの次の一文も、AIとともに──。
よくある質問(Q&A)
Transcopeは、キーワード分析・構成作成・文章生成までをAIが一括で行うSEO特化のライティングツール。 検索意図に沿った記事構成を自動で作れるため、記事品質を保ちながら制作時間を大幅に短縮できます。
▶ Transcopeの詳細を見るAIライティングツールに関する関連記事
▶︎AIライティングツールを比較してみる
- ChatGPTで磨く文章力|「伝わる言葉」をつくるAIライティング実践ガイド
- Catchy(キャッチー)完全ガイド|コピーから企画まで。AIが発想を支援するツール
- Value AI Writer by GMO|SEO記事生成AIで“検索に強い文章”をつくる
- BringRitera完全ガイド|SEO専門家が作った「成果を出す」国産AIライティングツール
- RakuRin完全ガイド|AIがSEO記事を「構造から生成する」国産ライティングツール
- CoWriter(コライター)完全ガイド|AIが記事を“共に書く”WordPress自動生成プラグイン
記事引用元・参考元
-
Transcope公式サイト
https://transcope.io/ -
株式会社なかみ「AI執筆ツール『Transcope』(トランスコープ)でつくってみた記事をプロが添削!使い方と料金」
https://nakami-fukuoka.com/column/transcope/ -
株式会社SUN GROW「Transcopeとはどんなツール?無料でできることと料金プランや使い方を解説」
https://www.sungrove.co.jp/transcope/ -
サクフリ「【評判】Transcope(トランスコープ)の口コミ・使い方・料金まとめ」
https://sakufuri.jp/media/transcope/ -
カメコンパス「Transcope(トランスコープ)の口コミ・評判まとめ」
https://www.kamecompass.com/transcope-reputation/ -
タツキングブログ「Transcopeとは?機能・料金・口コミまとめ」
https://tatuking.com/transcope/ -
ぎょぎょライティング「AIライティングツールTranscopeの実力をレビュー」
https://gyogyo-writing.com/transcope
ChatGPTで実現する再現性のあるSEOライティング設計