2025年10月31日、国立大学法人岡山大学の津島キャンパスにて、「OI-Start生成AI活用共有会」が開催されました。本イベントは、おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム(OI-Start)が主催し、岡山県高度情報化推進協議会が後援しました。OI-Start会員企業や岡山大学の教職員、学生など約130人が参加し、急速に進化する生成AIの活用事例や社内展開の課題を共有し、意見交換を通じて企業の発展と参加者間の交流を促進することを目的としています。
AI時代の展望と地域イノベーションへの期待
イベントの冒頭では、OI-Start会長を務める学術研究院環境生命自然科学学域の野上保之教授がインプットトークを行いました。野上教授は最新のAI事情に触れ、「この大AI時代に産業界として何ができるかを考え、岡山としての個性を発揮し、尖った取り組みをしていきたい」と語りました。
AI Workstyle Lab編集部より:
野上教授の言葉は、AIがもたらす変革期において、各地域や企業がどのように独自の強みを確立していくべきかという重要な問いを投げかけています。生成AIは汎用的なツールでありながら、その活用方法は無限大です。自社のビジネスモデルや地域特性と組み合わせることで、新たな価値創造の可能性が広がります。
多岐にわたる生成AIの企業活用事例
続いて行われた企業発表では、ピープルソフトウェア株式会社、株式会社協同、セリオ株式会社、株式会社ハイテックシステムズ、株式会社トスコ、コアテック株式会社の7社が登壇し、それぞれの企業における生成AIの活用事例を紹介しました。
事例としては、深層学習モデル(機械学習の手法の一つで、多層のニューラルネットワークを用いて複雑なパターンを学習する技術)を用いたワッペン画像の自動生成、生成AIの活用を後押しするためのガイドライン策定の経緯、さらには自社製AIツールの開発事例など、多岐にわたる内容が披露されました。また、生成AIサービスのデモンストレーションも行われ、参加者は各社の具体的な取り組みに触れることができました。


ソフトウェア開発における生成AIの現状と未来
企業発表の後には、学術研究院環境生命自然科学学域の門田暁人教授が「ソフトウェア開発における生成AI活用の現状と今後の展望」をテーマに講演しました。門田教授は、海外と日本における生成AIの現状を紹介し、今後の課題や生成AI時代のソフトウェア開発における展望について自身の見解を述べました。
AI Workstyle Lab編集部より:
ソフトウェア開発の現場では、生成AIの導入によってコード生成やテスト自動化など、多くの工程で効率化が期待されています。しかし、その一方で、セキュリティや品質管理、倫理的な課題など、乗り越えるべきハードルも存在します。今後の技術進化と適切な運用ルールの策定が、生成AI時代のソフトウェア開発の鍵となるでしょう。
活発な意見交換から見えた生成AI導入の論点
イベントの終盤には、オンラインツールを用いてリアルタイムで寄せられた質問をもとに、意見交換が行われました。「生成AIの新しい使い方」や「生成AI導入時のガイドライン策定」、「著作権に関する問題」、「地方である岡山で競争優位性を得るためには」など、多岐にわたるトピックについて活発な議論が交わされました。
野上教授は議論の締めくくりとして、「今日の発表を聞いて相互作用を促進し、AIという追い風を吹かせて、岡山ならではの個性を発揮してほしい」と参加者に期待を寄せました。


参加者の声とOI-Startの今後の展望
参加した学生からは、「大学院では植物の研究をしており、大きさ計測などにAIを活用しています。今、AIに遅れを取ると損だと感じており、こういった勉強の機会を得られて非常にありがたいです」との感想が寄せられました。これは、AIが専門分野を問わず、あらゆる研究やビジネスにおいて不可欠なツールとなりつつある現状を示しています。
今後もOI-Startは、産学官(産業界、学術界、官公庁が連携して活動すること)の垣根を越えた共創の場づくりを推進し、地域におけるイノベーションの創出に貢献していく方針です。地域中核・特色ある研究大学である岡山大学と、おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム(OI-Start)の今後の取り組みに注目が集まります。

AI Workstyle Lab編集部より:生成AIを仕事に活かすために
今回の「OI-Start生成AI活用共有会」は、生成AIが単なる技術トレンドではなく、具体的なビジネス課題解決や地域活性化に直結するツールであることを示しました。企業が生成AIを導入する際には、単にツールを使うだけでなく、自社の業務プロセスにどう組み込むか、どのようなガイドラインを設けるか、そして著作権などの法的側面をどうクリアするかといった多角的な視点が必要です。
AI Workstyle Labでは、このような実務的な情報共有の場が、AIを仕事に活かすための第一歩であると考えています。ぜひ、ご自身の業務や業界で生成AIの活用可能性を探り、積極的に情報収集や試行錯誤を重ねてみてください。地域を巻き込んだイノベーションの動きは、私たち一人ひとりの働き方にも大きな影響を与えることでしょう。
関連情報
- おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム(OI-Start)公式サイト:https://oistart.okayama-u.ac.jp/
- 岡山大学公式サイト:https://www.okayama-u.ac.jp/
- 岡山大学 関連ニュース:https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14769.html
- 岡山大学病院 新医療研究開発センター:http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/
- 岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当:http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/
- 岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部:https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
- 岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース(チーム共用):https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/
- 岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部:https://venture.okayama-u.ac.jp/
- 岡山大学オリジナルグッズ Online Shop:https://okadaigoods.official.ec/
- 岡山大学SDGsホームページ:https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
- 岡山大学SDGs~地域社会の持続可能性を考える(YouTube):https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
- 岡山大学Image Movie (YouTube):https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
- 岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS):https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/
「AIニュースは追っているけど、何から学べばいいか分からない…」 そんな初心者向けに、編集部が本当におすすめできる無料AIセミナーを厳選しました。
- 完全無料で参加できるAIセミナーだけを厳選
- ChatGPT・Geminiを基礎から体系的に学べる
- 比較しやすく、あなたに合う講座が一目で分かる
ChatGPTなどの生成AIを使いこなして、仕事・収入・時間の安定につながるスキルを身につけませんか?
AI Workstyle LabのAIニュースをチェックしているあなたは、すでに一歩リードしている側です。あとは、 実務で使える生成AIスキルを身につければ、「知っている」から「成果を出せる」状態へ一気に飛べます。
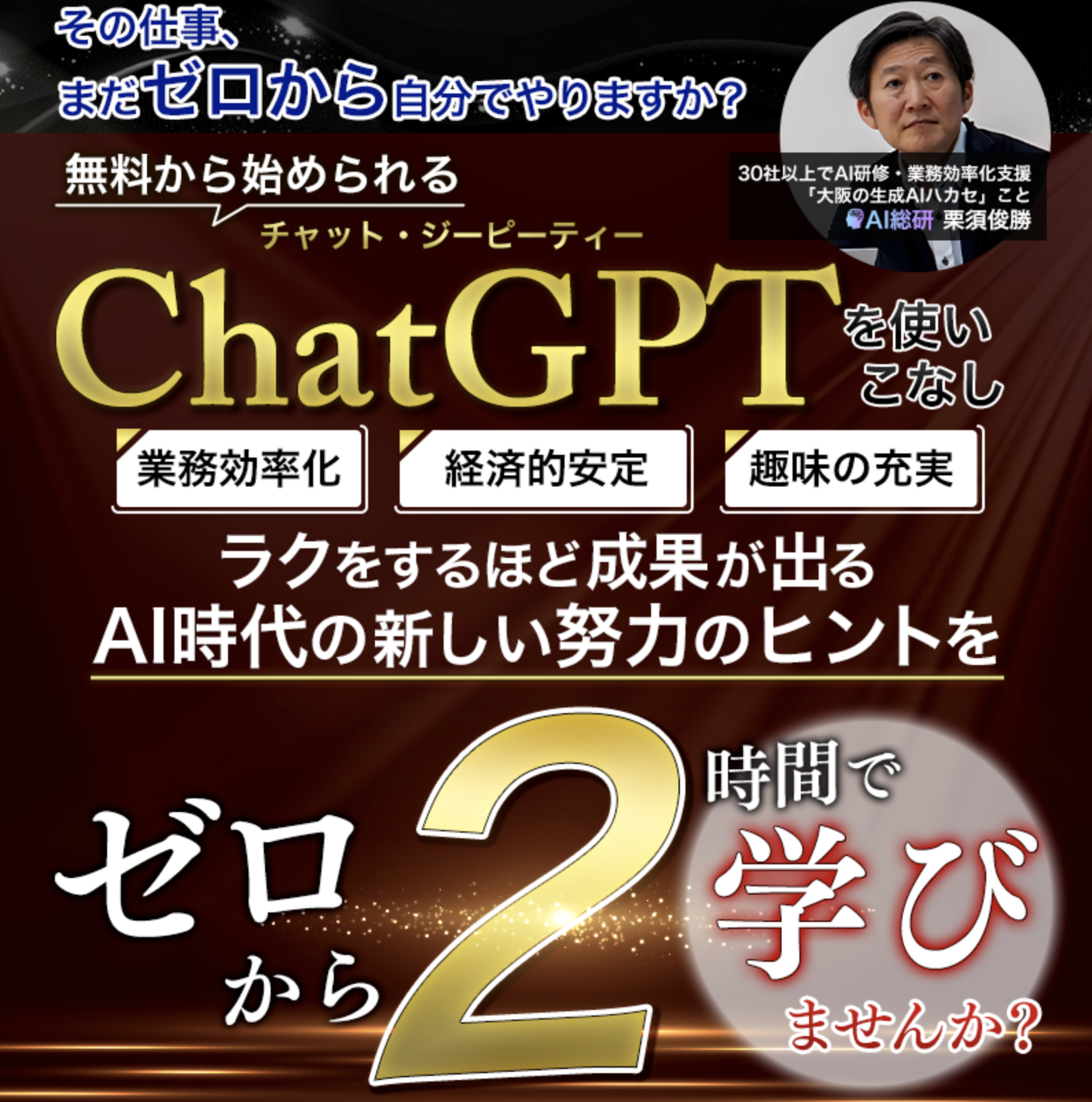
講師:栗須俊勝(AI総研)
30社以上にAI研修・業務効率化支援を提供。“大阪の生成AIハカセ”として企業DXを牽引しています。
- 日々の業務を30〜70%時短する、実務直結の生成AI活用法を体系的に学べる
- 副業・本業どちらにも活かせる、AI時代の「稼ぐためのスキルセット」を習得
- 文章・画像・資料作成など、仕事も趣味もラクになる汎用的なAIスキルが身につく
ニュースを読むだけで終わらせず、
「明日から成果が変わるAIスキル」を一緒に身につけましょう。
本記事は、各社の公式発表および公開情報を基に、AI Workstyle Lab編集部が 事実確認・再構成を行い作成しています。一次情報の内容は編集部にて確認し、 CoWriter(AI自動生成システム)で速報性を高めつつ、最終的な編集プロセスを経て公開しています。


